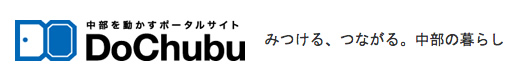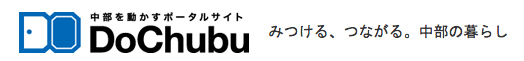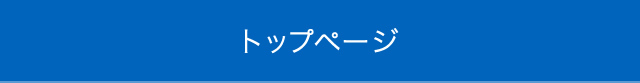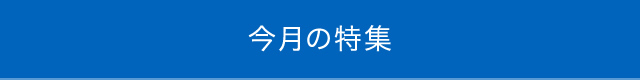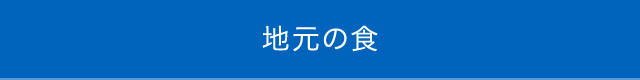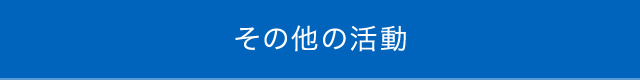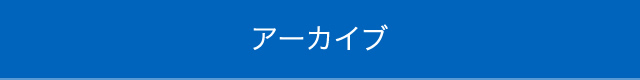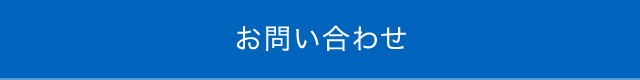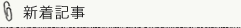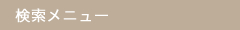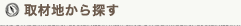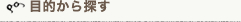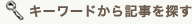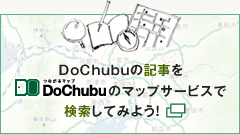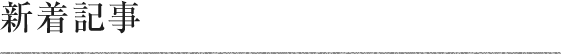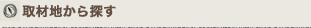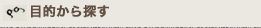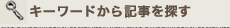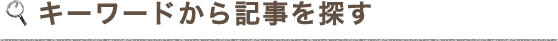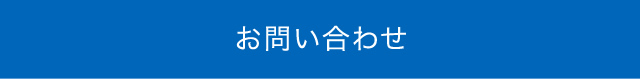耕作放棄地の再生に取り組む

揖斐川町の春日地域は、薬草の宝庫とされるところで、とくに古屋地区(上記写真の右下)では昔から暮らしに薬草を取り入れていました。
薬草の文化が色濃く残る地域で、薬草栽培を通して地域の活性化に取り組む「NPO法人山菜の里いび」の代表、小寺春樹さんにお話を伺いました。
薬草が暮らしの中に息づく地域
揖斐川町の春日古屋地区出身の小寺さんは、子どものときから薬草は身近にあったと言います。
昔は雪が降ると春まで外には出られないような不便な場所だったので、病気になっても簡単に医者へ行くこともできず、どこの家庭でも薬草を煎じて飲んでいたそうです。
「子どもの頃は、腹が痛いときはゲンノショウコを、熱が出たときはトウキなどを煎じて飲まされました。今でも、家ごとに様々な薬草をブレンドしたオリジナルの薬草茶があります。
また、薬草はお風呂に入れて薬草湯にします。私はヨモギを主に7種類の薬草を入れていますが、筋肉痛に効きますね」と小寺さん。
かつては「ひとまたぎ10種」と言われるほど、1歩進めば10種類ぐらいの薬草が見つかったという、この地域ならではの暮らしの知恵が今なお息づいています。

古屋地区では、軒先に薬草を干す様子が今でも見られます

ヨモギ湯に入ると血行が良くなると言われ、昔から入浴剤として使われてきたヨモギ
NPO法人を立ち上げ揖斐の自然をPR
サラリーマンとして地元を離れて生活していた間にどんどんと過疎化が進み、危機感を抱いたと語る小寺さん。耕作放棄地が増え、里山の景観が失われていくのを何とか止められないかと思い、平成19年に活動を始め、平成21年にNPO法人山菜の里いびを立ち上げました。
揖斐の自然にふれあう体験イベントを行う中で、伊吹薬草を体験するイベントなども開いてきました。

代表の小寺さん(左)と一緒に今年からスタッフとして活動を支える小寺雄俊(たけとし)さん。「祖父母の家がこの地域にあり、祖母が薬草などを煎じていた記憶があります」
ヨモギ栽培で耕作放棄地を減らす
5、6年ほど前からはヨモギの栽培に力を入れています。最初はタラ、フキ、ワラビなど山菜の栽培もしたそうですが、鹿の被害にあって全滅。そこで、ヨモギ栽培へ転向したと言います。
「山を歩いて鹿が食べていないものを探したところ、ヨモギが被害にあっていないことを発見したんです。残念ながら2、3年前からは鹿などに食べられてしまう被害が出ていますが…」。
ヨモギは伊吹の代表的な薬草ですが、地域の人々にとっては栽培するものではなく自生しているものでした。「薬草を栽培するというのは、この地域では初めての試みではないかと思います」。
耕作放棄地の活用とともに、高齢化が進む地域の人々に働く場所を提供したいという思いもあり、栽培や収穫、加工は地域の65歳以上の方々にお願いしているそうです。

ヨモギの畑。栽培面積は全部合わせて40アールほど

ヨモギは高さ40〜50センチほどになります

1枚1枚、ていねいに手で葉を摘み取ります。5月中旬から、7月、9月と、1年に3回収穫します
薬草・薬木を使った様々な取り組み
昔から身近にあったヨモギですが、国内ではヨモギの生産量が減っていて、国内で使われるヨモギは中国からの輸入品がほとんどだと言います。 現在は、生葉にして2トンを収穫できるまでになり、「冷凍ヨモギ」や「よもぎ粉」にして菓子店などにも卸しているそうです。
「よもぎ粉は、香りと色を残すのに苦労しましたね。繊維が強いので、粉末にするのも大変で…。ただ、伊吹のヨモギは香りが強く、パンや菓子などに入れても香りが残るため、お客さんからも好評です」。

「伊吹百草 よもぎ茶」とお菓子の材料としても人気がある「よもぎ粉」

ヨモギの粉末を練り込んだ「伊吹山麓 よもぎうどん」。「伊吹山麓 沢あざみうどん」は地元の伝統野菜サワアザミの粉末を練り込んだもの。どちらもモチモチ感が楽しめる米粉の麺です
※加工品は、山菜の里いびでメールinfo@npo-ibi.jpにて注文を受け付けています。消費税、送料が別途かかります。「伊吹百草 よもぎ茶」500円、「よもぎ粉」10g400円・20g800円、「伊吹山麓 よもぎうどん」「伊吹山麓 沢あざみうどん」各650円
また、かすがモリモリ村リフレッシュ館や揖斐川町内の道の駅、いび茶の里などでも購入できます
殺菌作用がある薬木のクロモジの栽培と活用も進めています。「クロモジは香りが良く、石鹸やエッセンシャルオイルへの利用を考えています。ただ、国内ではクロモジ栽培の実績がなく、試行錯誤を重ねてようやく本格的な栽培ができそうな段階まできました」。
クロモジやヨモギなどを練り込んだ石鹸の企画「伊吹の森石鹸 HERBAL SOAP」は、岐阜県が主催した平成26年度「清流の国・森の恵み大賞」の森の恵み部門で特別賞を受賞しました。現在、商品化に向けて準備を進めているところだとか。

可憐な花が咲くクロモジの木。樹皮などに香りの成分が含まれており、枝を折ると良い香りがします
また、昨年から「信長の薬草園プロジェクト」を始めました。かつて織田信長がポルトガル人宣教師の進言で、伊吹山に薬草園を開いたという話が伝えられています。これにちなんで、伊吹山の3合目に位置する古屋地区の耕作放棄地を薬草園にしようという活動です。
もともと、ヨモギ、トウキなどが自生していた場所ですが、土地を整備し、薬草の苗を植え付けました。「活動は始まったばかりですが、和のハーブである薬草を栽培することで耕作放棄地を救いたいと考えています」と、小寺さんは語ります。

信長の薬草園プロジェクトを進めている古屋地区

信長の薬草園などに植えるため、様々な薬草の苗を育てています
2015年4月17日取材時の情報になります。
ライター:田中マリ子
| 施設名 | 特定非営利活動法人山菜の里いび |
| 住所 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合3075番地1 |
| TEL | 0585-58-0230 |
| 営業時間 | |
| 定休日 | 土・日曜日 |
| info@npo-ibi.jp |